●先駆的科学計算に関するフォーラム2008 -分子科学計算「研究報告及び紹介と新システムへの声」
九州大学情報基盤研究開発センター主催
日時:2008年2月8日(金)10時00分~
場所:九州大学情報基盤研究開発センター多目的講習室(3階)
開催の主旨
電子状態理論および分子動力学などの理論化学,計算化学関連の若手の方々をお呼びして,最新の研究動向について議論する場を設けました.特に,コンピュータの動向と研究の方向性を議論する場になれば幸いです.一方,本年度から運用開始した新システムの利用に関して皆様のご意見をいただきたいと願っております.
日時:2008年2月8日(金)10時00分~
場所:九州大学情報基盤研究開発センター多目的講習室(3階)
開催の主旨
電子状態理論および分子動力学などの理論化学,計算化学関連の若手の方々をお呼びして,最新の研究動向について議論する場を設けました.特に,コンピュータの動向と研究の方向性を議論する場になれば幸いです.一方,本年度から運用開始した新システムの利用に関して皆様のご意見をいただきたいと願っております.
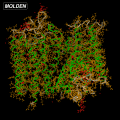 ロドプシン
ロドプシン